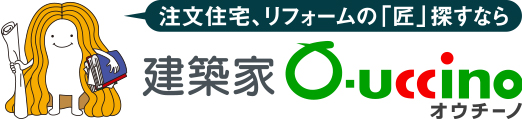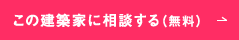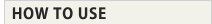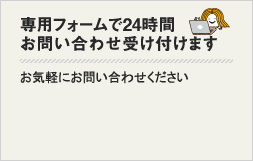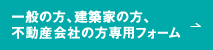建築家・ナイトウタカシさんのブログ「【車椅子】ドア?引き戸?使いやすいのは?」
【車椅子】ドア?引き戸?使いやすいのは?
2025/09/17 更新
家づくりやリフォームの打ち合わせで、意外と軽く扱われがちな「ドアの種類」。
しかし実際には、開き戸なのか引き戸なのか、その選択が毎日の暮らしやすさを大きく左右します。
特に車椅子生活や介助を伴う暮らしでは、その差は想像以上に大きなものになります。
1. 開き戸のメリットと落とし穴
開き戸は気密性が高く、音や匂いを遮るのに向いています。また、壁内に仕組みを作らずに取り付けられるため、建築コストが抑えやすい点も特徴です。
ただし、車椅子やベビーカーを利用する家庭では「扉を開けるために後退する必要がある」という大きなデメリットがあります。
狭い廊下や限られた空間では、開け閉めのたびに立ち往生してしまうことも珍しくありません。
さらに、扉の開く方向に家具や収納を置けないため、間取りの自由度も下がります。
2. 引き戸のメリットと課題
一方で引き戸は、扉をスライドさせるだけなので、車椅子でもスムーズに出入りができます。
開けっ放しにしても邪魔にならず、介助する家族と一緒に通過する場合も余裕が生まれます。
しかしデメリットもあります。気密性が低く音漏れしやすいこと、引き込みスペースが必要になるため設計の工夫が求められること、戸車やレールのメンテナンスが必要なことなどです。
3. 車椅子生活では「回転半径+ドアの種類」が重要
車椅子生活の場合、単に通れるかどうかだけでなく、「どう回転して進入するか」という点が重要になります。
たとえばトイレや浴室の前で方向転換が必要なとき、開き戸だと扉の可動範囲と車椅子の回転半径が干渉してしまい、非常に使いづらくなります。
引き戸であればその問題が大幅に軽減されるため、快適さは段違いです。
4. 介助のしやすさも左右する
家族が介助する場面でも、ドアの選択は大きな影響を与えます。
開き戸だと「扉を開ける→車椅子を押す→自分も通る」という一連の動作が煩雑になりますが、引き戸なら開けたままスムーズに二人で移動できます。特に夜間や急ぎの場面では、この違いが安全性にも直結します。
5. 将来を見据えた選び方
お子さんが成長する、介助する側の体力が変わる、車椅子が手動から電動に変わる――暮らしは常に変化します。
今の便利さだけでなく、将来の暮らし方を見据えて「どの場所にどの種類のドアを採用するか」を検討することが、後悔しない家づくりのポイントです。
まとめ
ドアは単なる出入り口の仕切りではなく、暮らしやすさそのものを左右する要素です。
開き戸は気密性・コストで優れるが、動線を阻害しやすい
引き戸は車椅子や介助に優れるが、設計・メンテナンスに配慮が必要
大切なのは、「家族の暮らし方」と「将来の変化」を踏まえて最適解を選ぶこと。
設計段階で生活動線シミュレーションを行えば、どの部屋にどんなドアを採用すべきかが明確になり、日々の快適さが大きく変わります。