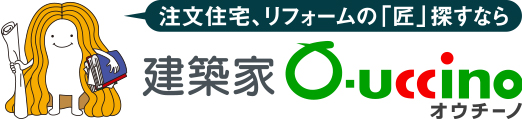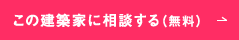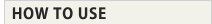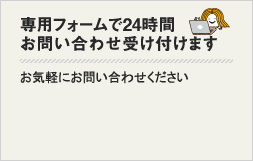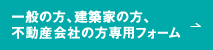建築家・ナイトウタカシさんのブログ「遮音材だけじゃ不十分?本当の防音計画」
遮音材だけじゃ不十分?本当の防音計画
2025/09/18 更新
「防音室をつくりたい」と考えるとき、多くの方が真っ先に思い浮かべるのは遮音材です。
壁に分厚いボードを入れたり、防音シートを重ねたりすれば、音は止められる──そんなイメージを持つ方は少なくありません。確かに遮音材は大切な要素のひとつですが、それだけでは十分な防音はできないのです。
遮音材の役割と限界
遮音材の役割は、文字通り「音を遮る」こと。
空気の振動を壁や床で食い止めることで、外に漏れる音を減らします。しかし、音は単純に「壁を通る」だけではなく、床や天井、隙間、配管、換気口など、あらゆる経路を伝わります。遮音材を壁に貼ったとしても、ドアの隙間や換気ダクトから音が漏れれば、防音効果は大きく損なわれてしまうのです。
さらに、遮音材は低音に弱いという特性があります。
グランドピアノの重厚な低音や、コントラバスの響きは、遮音材をすり抜けて床や構造体を通じて伝わります。結果、「思ったほど防音できていない」というケースは少なくありません。
本当の防音計画に必要な視点
では、どうすればよいのでしょうか?
ポイントは、防音を**「点の対策」ではなく「計画」**として捉えることです。
遮音(音を遮る)
壁や床を厚くするだけでなく、隙間処理・ドア・窓・配管周りの対策まで一体で考える。
吸音(響きを整える)
音が室内で跳ね返りすぎないよう、吸音パネルや天井材で適度に音を吸収。楽器ごとの音質を整える役割も重要。
構造(音の伝わり方を制御)
床や壁を二重構造にする「浮き床」や「二重壁」によって、建物自体を伝わる固体音を遮断する。
換気・空調との両立
防音室は密閉性が高くなるため、換気計画が不可欠。音を漏らさずに空気を入れ替える設計が必要。
これらを総合的に組み合わせてはじめて、安心して音楽を奏でられる環境が実現します。
暮らしと音楽を一緒に考える
防音室だけに集中すると、「防音はできたけど、暮らしに不便」という結果になりがちです。
例えば、収納が足りない、動線が悪い、採光が取れない──そんな状態では家族にとって快適な空間とは言えません。
だからこそ、防音室を単独で考えるのではなく、家全体の設計と同時に防音を計画することが大切です。楽器の特性・ご家族のライフスタイル・将来の使い方まで見据えたトータル設計が、本当の意味での「防音計画」なのです。
まとめ
遮音材は防音に欠かせない素材ですが、それだけでは不十分。
「遮音」「吸音」「構造」「換気・空調」まで含めた総合的な計画が、楽器を奏でる家庭には求められます。
そして、防音室単体ではなく家全体と暮らしを同時に考えることが、家族にとってもお子さまにとっても一番の安心につながります。
「音を抑える」だけではなく、「音を楽しむ」ための住まい。
それが、私たちが提案する「奏でる家」の防音計画です。