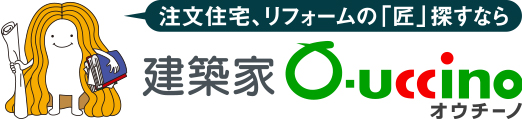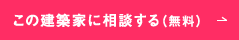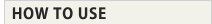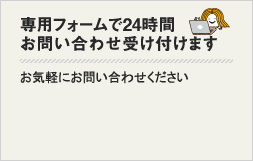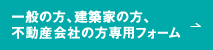建築家・ナイトウタカシさんのブログ「水回り共有の落とし穴と設計の進め方」
水回り共有の落とし穴と設計の進め方
2025/09/20 更新
二世帯住宅を考えるとき、多くのご家族が「水回りはどうする?」という問題に直面します。
キッチン・浴室・洗面・トイレ…。これらを親世帯と子世帯で共有するのか、分けるのか。
実はこの判断が、二世帯住宅の満足度を大きく左右します。
水回り共有のメリット
まずは良い面から見てみましょう。
コストを抑えられる
キッチンや浴室を二つ設ける必要がなく、建築費や設備費を削減できます。
省スペースにつながる
限られた敷地でも、共有にすればコンパクトな設計が可能です。
自然な交流が生まれる
一緒に料理をしたり、お風呂上がりに顔を合わせたりと、同居ならではの一体感を楽しめます。
共有の落とし穴
一方で、水回りを共有することで生じやすい「落とし穴」もあります。
利用時間が重なって気を遣う
朝のトイレや洗面所、夜の入浴時間など、生活リズムの違いが露呈します。
家事のやり方の違い
料理や掃除の仕方が異なり、ストレスの原因になることも。
匂い・音の問題
キッチンの調理音や浴室の換気音が、隣接空間に響くケースは意外と多いのです。
衛生観念の差
清掃頻度や使い方への考え方の違いが、摩擦を生むこともあります。
実際に二世帯住宅に住む方からも、「最初は共有で十分と思っていたけれど、毎日の小さな不満が積み重なった」という声は少なくありません。
設計のポイント
では、共有を選ぶ場合にどうすればストレスを減らせるのでしょうか。
設計上の工夫が大きな助けになります。
動線を工夫する
水回りを共有する場合でも、親世帯と子世帯のアクセス動線を分けることで、利用時の気まずさを防げます。
“サブ水回り”をつくる
洗面台や小型キッチンをサブ的に設ければ、混雑時のストレスを軽減できます。
収納と設備を世帯別に
タオル・調理器具・掃除用品などは世帯ごとに収納スペースを分けておくと、日々の小競り合いを避けられます。
防音・換気の工夫
壁や床に遮音材を入れる、換気扇を強化するなど、生活音や匂いが伝わりにくい工夫は効果絶大です。
将来の分離を見据える
最初は共有でも、将来必要に応じて分けられるように配管やスペースを確保しておくと安心です。
まとめ
水回りを共有するかどうかは、二世帯住宅の「距離感」をどう設計するかに直結します。
共有のメリットは費用やスペースの面で大きいですが、その一方で生活リズムや価値観の違いからストレスを生みやすい面も否めません。
大切なのは、設計段階でどこまで共有するか、どこを分けるかを明確に決めること。
さらに、将来の変化にも柔軟に対応できるような余白を残すことです。
二世帯住宅は「建物を共有する」だけでなく、「暮らし方をデザインする」こと。
ご家族にとって最適な距離感を探ることが、同居ストレスを回避し、長く快適に暮らす秘訣です。