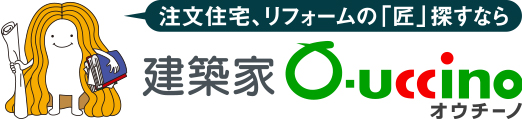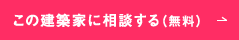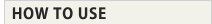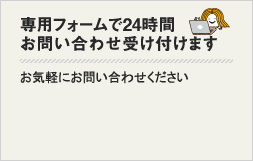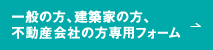建築家・ナイトウタカシさんのブログ「【奏響の家】窓とドアで、防音は決まる」
【奏響の家】窓とドアで、防音は決まる
2025/11/06 更新
「壁を厚くすれば音は漏れない」──そう思っていませんか?
実は、防音性能を大きく左右するのは窓とドアです。
どんなに壁や床をしっかり施工しても、音の出口となるこの2か所の対策が不十分だと、“音の逃げ道”ができてしまいます。
1. 音は「空気」と「すき間」から漏れる
音は空気の振動です。
つまり、わずかなすき間があるだけで、そこから簡単に漏れ出してしまいます。
特に窓やドアのまわりは、構造上、開閉に必要な“遊び”があるため、壁よりも弱点になりやすい部分。
いくら防音パネルを使っても、窓やドアの性能が低ければ、「外に音が漏れる」「外の音が入る」どちらの問題も解消できません。
2. 窓は“ガラス”より“構造”が大事
防音性能の高い窓というと、「二重ガラス」や「防音ガラス」を思い浮かべる方が多いでしょう。
もちろんそれも効果的ですが、ポイントは“ガラスの厚み”と“サッシの気密性”のバランスです。
例えば、外側と内側のガラスの厚みを変えた“異厚複層ガラス”は、異なる周波数の音を打ち消し合うため、ピアノやヴァイオリンなどの幅広い音域に効果があります。
さらに重要なのがサッシの構造。
一般的なアルミサッシよりも、樹脂製や防音専用サッシの方がすき間が少なく、
高い遮音性を発揮します。
「窓は光を入れるもの」と同時に、「音を制御する装置」でもあるのです。
3. ドアが“音の漏れ口”になりやすい理由
防音室のドアは、一般的な室内ドアとまったく構造が違います。
厚みがあるだけでなく、ドアの縁に気密パッキンが施され、閉めた瞬間に“密閉”される仕組みになっています。
このパッキンが劣化したり、建付けが悪くなったりすると、そこから一気に音が漏れてしまうため、定期的な調整も必要です。
また、ドア下のわずかなすき間からも音は逃げます。
プロ仕様の防音室では、ドア下に自動ドアボトム(閉めると自動ですき間をふさぐ装置)を設けるなど、細かな工夫がされています。
4. 家全体で考える「開口部防音」
窓やドアの防音は、部屋単体の問題ではありません。
家全体の開口部の配置──たとえば「防音室のドアが廊下を介してリビングにつながるのか」
「窓が隣家に面しているのか」などによっても効果が大きく変わります。
建築家と音の専門家が連携すれば、“閉じるための防音”ではなく、“暮らしの中で音が整う設計”が可能です。
まとめ
防音の鍵は、壁の厚みよりも窓とドアの精度にあります。
つまり、「見えないすき間をどれだけなくせるか」が、防音の完成度を決めるのです。
お子さまの音が、安心して家の中に響くために。
防音室づくりは、まず「開口部」から見直してみてください。