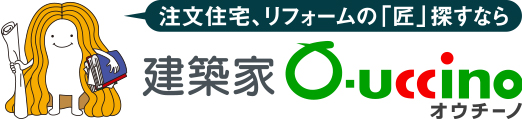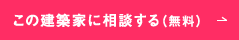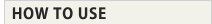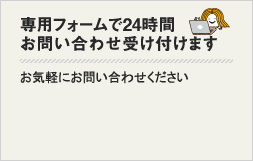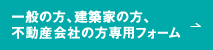建築家・ナイトウタカシさんのブログ「空気の振動と床の響きを同時に考える」
空気の振動と床の響きを同時に考える
2025/11/13 更新
ピアノやヴァイオリンの音が思いのほか外に漏れる。
また、上階の足音や振動が下の階に響いてしまう──。
防音のご相談でよく聞くこの2つの悩み。
実は、どちらも「空気の振動」と「床の響き」という、音の“伝わり方”の違いに関係しています。
1. 音には2つの伝わり方がある
音は、空気を震わせて伝わる「空気伝播音」と、
建物そのものを震わせて伝わる「固体伝播音(構造伝播音)」の2種類があります。
たとえばピアノを弾いたとき、音そのものは空気中を伝わりますが、
床や壁を通じても“振動”が家全体に広がっていきます。
つまり、防音を考えるときには、
この2つの経路を同時に遮断・調整しなければ、
いくら壁を厚くしても“音が回り込む”現象が起きてしまうのです。
2. 空気の振動には「密閉」と「吸音」
空気伝播音を抑えるために大切なのは、すき間をなくすこと。
ドアや窓の気密性を高め、音の通り道をなくすことが基本です。
そのうえで、壁や天井に吸音材を入れ、
音の反射を和らげて響きを整えます。
ただし、吸音しすぎると音がこもって聴きづらくなるため、
“どの音域をどれくらい吸うか”の調整がポイント。
ピアノとヴァイオリンでは音の性質が違うため、
楽器ごとに最適な音響バランスを設計することが大切です。
3. 床の響きには「浮き構造」という工夫
もう一方の「固体伝播音」に効果的なのが、**浮き構造(フローティング構造)**です。
これは、床や壁を建物の構造から“少し浮かせて”設置する方法。
防振ゴムや遮音マットを間に挟むことで、振動が構造体に伝わりにくくなります。
ピアノの低音のように“床から響く音”は、この構造によって大きく軽減できます。
ただし、浮き構造は重量や天井高に影響するため、
家全体の設計と一体で考える必要があります。
「防音室だけ後から浮かせる」というのは難しく、
新築時に建築家と音響専門家が連携しておくのが理想です。
4. 音は“閉じ込める”より“整える”
防音の目的は、音を完全に閉じ込めることではありません。
家族の暮らしと調和しながら、
“心地よい響き方”をつくること。
空気の振動と床の響きの両方を考えた設計なら、
家の中に静けさを保ちながら、演奏の余韻を美しく残すことができます。
まるでコンサートホールのように、音が自然に呼吸する空間。
それが、本当の意味での「防音設計」です。
まとめ
防音室づくりは、壁の厚さではなく、音の伝わり方の理解から始まります。
空気の振動と床の響きをバランスよく整えることで、
“静けさ”と“響き”が両立する家になる。
お子さまの音楽が、家族の心に心地よく響く。
そのためにこそ、建築と音の専門家が一緒に考える価値があるのです。