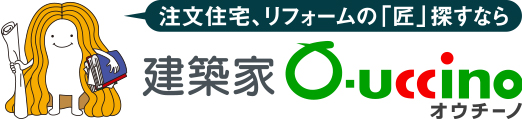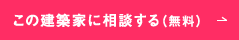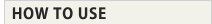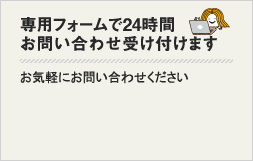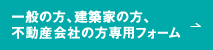建築家・ナイトウタカシさんのブログ「家の中の「におい」を科学する」
家の中の「におい」を科学する
2025/11/14 更新
家に帰ってドアを開けた瞬間、ふと感じる“におい”。
それは、その家の「空気の履歴」を物語っています。
食事、洗濯、湿気、ペット、そして人の体温。
毎日の生活で生まれるにおいは、実は空気の質と密接に関係しています。
「におい」は単なる不快感ではなく、家の“健康状態”を知らせるサインでもあるのです。
においの正体とは?
においの多くは、**揮発性有機化合物(VOC)**と呼ばれる微粒子です。
料理の油煙、洗剤や芳香剤、建材や家具の接着剤などから発生し、空気中に漂うことで鼻がそれを“におい”として感じます。
とくに密閉された現代の住宅では、これらが外へ逃げにくく、「なんとなくこもったにおい」の原因になってしまうのです。
一方で、湿度の高い場所ではカビや雑菌が発生しやすく、それが分解される過程で“カビ臭”“湿気臭”といった不快なにおいを発します。
つまり、においとは空気の中の化学変化。
感じ方の問題ではなく、住まいの環境そのものの問題なのです。
においを抑える家のつくり方
① 「発生源を減らす」
調理中の換気扇を必ず使用する、洗濯物をためない、排水口を清掃する。
こうした日常の積み重ねが最も効果的な予防策です。
また、芳香剤でごまかすのは一時的な対応。
人工香料を重ねると空気の成分がさらに複雑化し、かえって“混ざったにおい”が生じることもあります。
② 「空気を動かす」
空気がよどむと、においは滞留します。
風の通り道を意識した間取りや、24時間換気システムのバランスを見直すだけで、においの蓄積は大幅に減ります。
すくわくハウスでは、空気の流れをシミュレーションし、においがこもらない「呼吸する家」を設計しています。
③ 「においを吸う素材を使う」
漆喰や珪藻土などの自然素材には、有害物質を吸着・分解する効果があります。
調湿性能も高く、湿気とにおいを同時にコントロールできるのが特徴です。
また、無垢の木には木種ごとの自然な香りがあり、空気にやさしい“生活の香り”をつくり出してくれます。
においは“感性”のデザインでもある
実は、「いいにおいの家」には科学的な裏づけがあります。
においのない清潔な空気は、人の集中力を高め、不快臭のない環境はストレスを減らすといわれています。
だからこそ、私たちは“におい”を感覚的なものではなく、**設計でコントロールすべき「空気の質」**として扱っています。
まとめ
においを消すのではなく、においの「理由」を知り、空気から整える。
それが、家族が安心して深呼吸できる住まいの第一歩です。
見えない空気を、感じられる心地よさに変える。
それが、すくわくハウスの「空気をデザインする家づくり」です。