こだわりポイント
多くの所要室を中庭の周りに配置することで、効率よく回遊性のあるプランニングを行いました。ランニングコストの削減と、輻射による体感の良い空調を行うため、建物の床下全面に敷設した蓄熱・蓄冷ユニットにより冷暖房を行うシステムを導入しています。
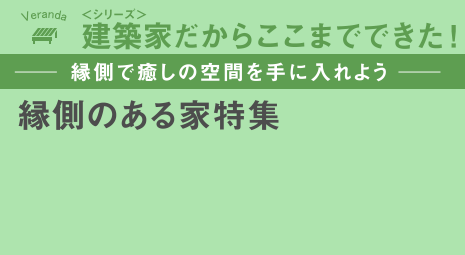
昔ながらの暮らしの象徴と言える「縁側」。ネコがひなたぼっこしたり、おじいちゃんが将棋をしたりといったイメージがすっかりが定着しています。そんなゆったりとした生活への憧れなのか、実はいま、縁側のある家を造ろうとする人が増えています。現代の縁側とは、一体どんなものなのでしょうか?
縁側とは、座敷から外側に張り出した細長い板張りのこと。日本家屋の独特の造りです。屋内と屋外のどちらでもない空間として、昔から日本人の生活の中に溶け込んでいました。
たとえば、部屋から出て縁側に座れば、外に出ることなく庭の風景を楽しむことができます。また縁側があることで、庭で仕事をしている家族や遊んでいる子どもともコミュニケーションがとれます。日当たりもいいので、ひなたぼっこをしながら会話をしたりと、縁側は家族のつながりを深めてくれるでしょう。屋内と屋外の中間という「あいまいさ」がいいのです。
夏であれば、室内から縁側に出ればすぐ外の風に当たることができます。夕方に縁側で夕涼みをしたりすれば、クーラーの部屋にこもっているより健康的な生活と言えます。冬場は日照時間が短くなって生活リズムが乱れがちですが、縁側で日光浴をしたり、軽く体を動かしたりと、体調管理の面でもプラスになってくれるでしょう。
和風建築にとって、縁側は見どころの1つです。家族のだんらんはもちろん、来客があったときやお祝いなどのイベントでも、縁側は人が集まる交流場所となります。当然ながら、多くの人の目に触れることにもなるので、庭や屋内との調和を考えて、いいプランを考えましょう。
ポイントは、縁側から見える風景です。縁側を使うときは、ほとんどの場合、庭の方を向くことになります。そのときの景色が気持ちのいいものであるかどうかが、縁側の質を左右するのです。完全な屋内ではないので、内装や機能性より、「そこからなにが見えるか」が大切になってくるわけですね。庭のデザインはもちろん、きちんと枝の剪定(せんてい)をしたり、雑草を抜いたりといった「手入れ」も必要になってくるでしょう。縁側を快適な場所にできるかどうかは、住み手次第と言えます。
実際に縁側のある家のプランを作るときは、敷地や建ぺい率に余裕を持たせておかねばなりません。日本家屋に詳しい建築家に相談するのがいちばんです。
建築家がさまざまな工夫を凝らしデザインをした、縁側のある家の作品をラインナップしてお届けします。
多くの所要室を中庭の周りに配置することで、効率よく回遊性のあるプランニングを行いました。ランニングコストの削減と、輻射による体感の良い空調を行うため、建物の床下全面に敷設した蓄熱・蓄冷ユニットにより冷暖房を行うシステムを導入しています。
外部に対して一切の開口を持たない黒い箱は内部に設けたライトコート(光の庭)で全ての居住空間を光で満たす計画としています。建物の機能形態はガレージハウス。 生活空間とクルマ空間の間にライトウェル(光の井戸)を設け、付かず離れずの曖昧な距離感を演出しています。
既存の住まいの和室14帖(8帖と6帖)を基準として、空間の構成を行いました。サッシを開け放つと広い縁側が広がり、明るく開放感のある構成としています。 2世帯をつなぐダイニングは和室(親世帯)と2階(子世帯)への階段の中間にあり、吹抜けやブリッジのあるダイナミックな空間としています。
Copyright© O-uccino, Inc. All Rights Reserved.